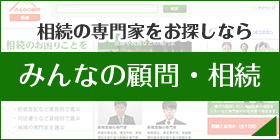私が考える顧問選びのコツ
| 企業経営者や資産家、プロフェッショナルにとって、専門外の分野や領域に心強い味方がいれば、さらに本来の力を発揮できることができるはず。 一方で、積極的に企業の経営戦略に関わろうという専門家も増えてきました。 ここで困るのが顧問の選び方です。 単なるアウトソーシング先ではない顧問を探したい、しっかりした顧問が欲しいという読者向けに、各界のプロが顧問選びのポイントを伝授します。 |
東京・大田区蒲田に原&アカウンティング・パートナーズ(原会計事務所)をかまえる税理士の原尚美先生。今回は原先生に顧問選びについてお話を伺いました。 (編集部) |

顧問と「価値観が合うかどうか」
私は、顧客と専門家のお互いの価値観が合うことがとても重要だと考えています。
私の場合は、会社を大きくしようと願う野心のあるお客様が合っているようです。
節税を考えるのも会社にとっては大切なことですが、私は「会社を成長させる」ことを優先して考えます。税金は会社を拡大するためのコストだと。資金繰りとしての節税なら意味がありますが、節税自体を目的とする出費には興味がありません。このような価値観が合うかどうかが、大事だと思います。
顧問の「仕事が早いかどうか」
ひとつのことを何日経ってもできない人もいます。私の場合は、目の前にある仕事はすぐに片付けないと気が済みなせん。
お客様によっては、「間に合えばそれでいい」という方もいらっしゃるでしょう。しかし依頼者の仕事に対するスピード感が早い場合、仕事の遅い先生を顧問にしてしまうと、毎回イライラしてしまうことになります。
顧問が「柔軟に対応できるかどうか」
会計事務所の場合、顧問先に税金以外のことは相談できないと思っていらっしゃるお客様は多いと思います。
しかし、給与計算や資金調達、経営相談などに対応してくれる税理士もいるのです。遠慮することなく、どんどん相談してほしいと思います。
顧問が「一生懸命かどうか」
私たち自身がお客様と長期的な信頼関係を築くことができたのは、「一生懸命にやってくれている」と思っていただけたことだと思います。お客様のためにどこまでも親身に動くことが、私たちの仕事だと考えています。私たちの仕事の楽しさの原点は、お客様の「ありがとう」のそのひとことです。それですべての苦労が報われるのです。
回答者プロフィール

原尚美(はら・なおみ)さん
税理士
東京外国語大学英米語学科卒業。7人家族の専業主婦から税理士を目指す。1987年、東京都大田区蒲田に事務所を設立。2013年に、ミャンマーの都市・ヤンゴンに現地法人を設立。
著書に「51の質問に答えるだけですぐできる『事業計画書』のつくり方」(日本実業出版社)、「世界一ラクにできる確定申告」(技術評論社)、「会社のつくり方がよくわかる本」、「小さな起業のファイナンス」(ソーテック社)、「トコトンわかる株式会社のつくり方」(新星出版社)、「一生食っていくための士業の営業術」(中経出版)など多数
| 企業経営者や資産家、プロフェッショナルにとって、専門外の分野や領域に心強い味方がいれば、さらに本来の力を発揮できることができるはず。 一方で、積極的に企業の経営戦略に関わろうという専門家も増えてきました。 ここで困るのが顧問の選び方です。 単なるアウトソーシング先ではない顧問を探したい、しっかりした顧問が欲しいという読者向けに、各界のプロが顧問選びのポイントを伝授します。 |
今回の回答者は、『5分会議』を提唱・活用した実績のある人財育成家の沖本るり子さん。講師選定を例に、顧問選びのコツをお教えいただきました。 (編集部) |

紹介からの依頼
私の事務所では、私の著書や雑誌の連載を読んで仕事を依頼される方もいらっしゃるのですが、ご紹介が多いです。突然業績を上げた企業に取引先がその理由を聞いて、たどり着くといった経緯などから長くお付き合いをさせていただいています。信用できる取引先からのご紹介というのは有力な手段です。
しっかりした力量の専門家を迎え入れる
講師選定の場合は、コンテンツの根拠をしっかりと語れる人を選ぶことが重要です。講師の中にはいわゆる受験生タイプ、「自分はこう教えてもらったのだから、みなさんもこうしてください」という人や、教科書や本を丸暗記しただけのような人がいます。しかし、それでは現実的、合理的な対応ができません。実力のある専門家を選ぶようにしてください。
肩書きや経歴だけで人物を見ない
スポットではなく、顧問として迎え入れるのであれば、なおさらしっかりとした能力が必要です。ここで気をつけなければならいのは、ただ経歴が長いだけではその人が優秀であるとは限らないことです。
では、どうすれば力量が測れるかというと、面接などで講師と直接お会いする際に知ることができます。たとえば、現状に合わせたカリキュラムのアレンジに対応できるかどうかという質問をすると、丸暗記型の講師では対応できないのです。
質問で「理解力」や「対応能力」を知る
研修や講習で、「法則」を口にする講師は多いものです。たとえば「メラビアンの法則」について、よくマナー講師が口にします(※)。しかし、その背景について実は多くの講師がわかっていません。つまり、本当の意味を理解しないでその言葉を使っているのです。
法則やルールを口にする講師の実力を知りたければ、どのような調査でその法則が生まれたのか、経緯を質問してみてください。これにきちんと答えられれば、合格です。
以上は講師選びでの一例ですが、質問によって力量を測るというのは、どの顧問選びでも有効なはずです。みなさんが、よい顧問に出会えることを願っています。
※心理学者アルバート・メラビアンによる実験、研究への俗流解釈。
回答者プロフィール
沖本るり子(おきもと・るりこ)さん
人財育成・組織改革コンサルタント。
株式会社CHEERFUL代表取締役。『5分会議』を活用したリーダー力やチーム力を向上させる人財育成や、組織活性の講習を行っている。著書に『相手が“期待以上"に動いてくれる! リーダーのコミュニケーションの教科書』(同文館出版)、『リーダーは話を1分以内にまとめなさい』(中経出版)、『出るのが楽しくなる! 会議の鉄則』(マガジンハウス)など。
| 企業経営者や資産家、プロフェッショナルにとって、専門外の分野や領域に心強い味方がいれば、さらに本来の力を発揮できることができるはず。 一方で、積極的に企業の経営戦略に関わろうという専門家も増えてきました。 ここで困るのが顧問の選び方です。 単なるアウトソーシング先ではない顧問を探したい、しっかりした顧問が欲しいという読者向けに、各界のプロが顧問選びのポイントを伝授します。 |
今回の回答者は、神奈川県川崎市の落合和雄税理士事務所の落合和雄先生。専門家に顧問になってもらい、心強い味方を得るコツについてお話を伺いました。 (編集部) |

「専門外の専門家」に依頼しないように注意する
自分が相談する分野に強い専門家かどうかを見極めることが大切です。顧客から税理士、弁護士への不満を聞かされることがありますが、それは専門外の方に頼んでしまったケースがほとんどです。
たとえば、経営支援を期待するのであれば、経営に強い税理士に頼む必要があります。
本当の専門分野を探す際のポイント
顧問捜しをする際には次のことを頭に入れておくとよいでしょう。たとえば、アピールする看板の冒頭に「相続」と書いてなければ、相続は専門外の税理士です。後ろのほうに「相続」とあると、単なる箔付けの可能性があります。たいして力を入れていない分野の場合があるので注意してください。
経営全般の支援を期待できる税理士を選ぶことも大切です。ほかの分野とのネットワークを持っていて、最適な司法書士、弁護士、社労士などを紹介してもらえれば大きな助けになります。
顧問はどこまで手を貸してくれるのか?
私の事務所では、経営支援までをワンセットで行います。会社の経営を常にチェックし、借入金の対策などを経営者と一緒に考えます。経営会議にも定期的に参加しています。しかし、税理士の立ち位置は税理士によって違います。定期訪問をしない、経営支援をやらないという税理士もたくさんいます。
私は、税理士というものは節税対策をするのは当たり前だと考えています。しかし、別の税理士事務所から来られた顧客から「こういうこともやってくれるのですか!」と驚かれたことがありました。
自分が望む専門分野の士業の先生であっても、どこまで手を貸してくれるのかをはっきりとさせておくのは大事なことだと思います。
回答者プロフィール

落合和雄(おちあい・かずお)さん
税理士。
システムエンジニアを経て、MBA(経営情報学修士)を取得。税理士としての活動を中心に、中小企業診断士やITコーディネータ等の資格も併せて、創業支援・経営計画立案・企業再建等の経営指導やプロジェクトマネジメントのコンサルティングを行う。著書に「実践ナビゲーション経営」(同友館)、「年金に頼らない蓄財術」(アスキー新書)など。
| 企業経営者や資産家、プロフェッショナルにとり、専門外の分野や領域に心強い味方がいれば、さらに本来の力を発揮することができるはず。 一方で、積極的に企業の経営戦略に関わろうという専門家も増えてきました。 ここで困るのが顧問の選び方です。 単なるアウトソーシング先ではない顧問を探したい、顧問が欲しいという読者向けに、各界のプロが顧問選びのポイントを伝授します。 |
「顧問選びのコツを教えてください」という編集部の要望に快くお答えいただいたのは、日本橋に石橋税理士事務所を構える税理士の石橋將年先生。石橋先生に「税理士の顧問選び」を伝授していただきました。 (編集部) |

1.優先順位を決めましょう
税理士に限らず、どんな人間にも長所・短所があります。選ぶ際の項目ですが、一般的には次のようになると思います。
- 年齢(自分と同じくらいの年齢か?)
- 性格(感じが良いか? 分からない事を気軽に聞けそうか?)
- 報酬(費用は相場から外れていないか?)
- 専門知識(特定の分野について他の税理士よりも知識・経験が豊富か?)
- 立地(自宅や職場から近いか?)
全ての条件を満たす税理士を探してはいけません。そんな税理士はいませんから(笑)。
ですので、自分なりの優先順位をつけるのですが、私が選ぶ際は、つぎの優先順位で決めるでしょう。
性格>年齢>専門知識>立地>報酬
「専門知識が最優先じゃないの?」というご意見があるかもしれません。ですが、その専門知識を聞く際に、聞きづらい税理士であっては、お願いする意味がありません。ですので、まずは性格(聞きやすさ)と年齢を重視して選んでみましょう。
2.ホームページを見る際のポイント
(1)本人の写真を見る
私であれば、最初に写真を見ます。もちろん、写真では性格は分からないのですが、迷ったときは、最後は直感になるかと思いますので。笑った写真があると、こちらも安心ですよね。
(2)専門知識があるか?(分かりやすい記事+自分の経験を語る記事)
記事の質といっても、難しく考える必要はありません。簡単な言葉で分かりやすく説明しているかを見れば良いのです。逆に、難しい用語(例えば、選別する・認定する・適用する)が多くあるようなら、きちんと説明してもらえるのか、不安ですよね。
また、「○○という事例があって困ったが、○○のように解決した」というように、自分の経験を書いた記事が多くあると、経験値が高い専門家といえるかもしれません。
3.アポイントを取る際はどうすればよい?
電話やメールで聞くべき項目としては、次が挙げられます。
- 相談内容(確定申告・会社決算といった、具体的にお願いしたい事項)
- 相談料(初回相談料は無料なのか?)
- 相談日時(平日だけでなく土日も可能か?)
本命の税理士には、お電話でアポイントを取るほうが良いかもしれません。
というのは、電話の応対で、ある程度、事務所の雰囲気が分かるからです。また、インターネットからのお問い合わせに慣れている事務所であれば、問題のポイントを整理してくれるでしょうし、メールの返信も早いと思います。
ただし、ご注意頂きたい点があります。
それは「無料相談だけが目的ではなく、きちんと依頼の意思がある」ということを伝えることです。
依頼するお気持ちがあるのに、相談内容や予算の関係で成立しなかった。それは全く問題ありません。
ですが、なかには(とても少数ですが)聞きたいことだけを無料で聞こうという方もいらっしゃるんですね。ですので、その点にはお気をつけください。
4.相談当日の心構え
初回の相談時に注意して頂きたいのが、「質問の内容が期待通りでなくても、それだけで判断しない」ということです。
私がお受けする相談のなかに「現在、不動産投資をしているが、不動産管理会社を設立して節税したい」というものがあります。たしかに会社を設立すれば節税になるのですが、同時に社会保険料の負担が発生してしまいます(会社が役員にお給料を払う場合、そのお給料に高い率の社会保険料がかかるのです)。
税理士のなかには、そのことを知っていて(または本当に知らないで)安易に会社設立を勧める方もいらっしゃいます。会社設立すれば、税理士は報酬をもらえるのですから。
ですが、私の方針としては、税金だけを考えず、「税金+社会保険料」のトータルの負担で会社設立を考えます。ですので、私がご相談にのると、そのことをご説明し、いったんお帰り頂く事が多いです(私には1円も入りませんが、その方が相談者様のためになるからです)。
それらのことは、相談者様にはすぐには分からないかもしれません。ですので、相談中の税理士の態度や口調を見て、「この税理士は自分のことを心配してくれそうかな?」ということを第一に選ぶのが良いかと思います。
5.税理士が嬉しくなってしまう依頼者とは?
- 全てをお話し頂ける方(売上等を隠されても困りますので・・・)
- ある程度、税理士にお任せ頂ける方(人はお願いされると全力を尽くすものです)
- 前の税理士先生の悪口を言わない方(こちらも陰で悪口を言われると思うと、モチベーションが下がります・・・)
以上、私が考える税理士選びのコツについてご説明してまいりました。繰り返しになりますが、まずは人柄、それから専門知識を確認してみてください。
他の資格(弁護士等)と違い、税理士との契約は長期になることが多いです。税理士をご紹介で探す方も多いと思いますが、その場合は、「断りにくい」「専門知識の有無」といったことが問題になると思います。
ぜひ、ホームページで気に入った税理士があれば、積極的にお会いしてみてください。皆様にとって、良い税理士先生が見つかることをお祈り申し上げます。
回答者プロフィール

石橋將年(いしばし・まさとし)さん
東京都中央区築地出身。実家は築地市場で乾物屋を営む。
都内2カ所の税理士法人・会計事務所で十数年の実務経験を積み、東京都中央区日本橋茅場町にて平成23年に石橋税理士事務所を開業。
実家の商売上の様々な問題に直面し、また、実家での不動産賃貸業の経験を生かし、サラリーマン税理士にはできない、相手の立場に立った親身なアドバイスには定評がある。主な顧問先は中小企業・個人事業者・不動産オーナー・地主・士業(弁護士・弁理士等)・医師等。
「作業」よりも「相談」に重きをおいて仕事をするがモットー。
文:ランチェスター社労士 川端康浩
「信頼できる顧問の選び方」の第3回目です。
※過去の記事はこちら
【第一回】士業の事務所の選び方とは!
【第二回】税理士にも経営コンサルティングの知識が求められている!
今回は顧問先から選ばれるための士業にとっての経営戦略や付加価値について考えます。

士業の競争激化
最初に、士業にとって一番大事なのは、「専門領域」の基本商品です。
その基本商品とは、税理士であれば税の申告業務、社労士であれば労働法令に関する業務です。
この専門領域の基本を外すことはできませんが、お客さんが求めるニーズはその先にあります。そこで考えたいのが士業にとっての経営戦略です。
世の中に商品や情報が溢れている現在、モノを買おうと思えば、いくらでも購入することができます。
もし、あなた自身が購入者だとしたらどうでしょうか。
何かの商品を購入しようというときに、市場に同じ商品があった場合、少しでも安いほうを買おうとするでしょう。
しかし、売り手側にとって、適正な売上や利益を得ることができるでしょうか。
これは士業にとっても同じです。
大量生産販売で効率化が図れる巨大資本のメーカーならいざしらず、士業のような人的サービス業が価格競争に巻き込まれると、適正な売上や利益の確保が大変難しくなります。
何十年も以前は、需要に対する士業の絶対数が少なく、競争になりにくい面がありました。しかし毎年毎年、資格試験が行われ、合格者の中から必ず一定数の開業者が現れます。時を経るに従い同業者が増えますので、競争は増すばかりです。
同質化した商品を販売し合う競争状態になると、決まって発生するのが「価格競争」ですが、有資格者同士での同質化の戦いから抜け出る方法が必要です。
文:ランチェスター社労士 川端康浩
「信頼できる顧問の選び方」の第2回目です。
(第1回はこちら:【信頼できる顧問とは第一回】 士業の事務所の選び方とは!)
士業と呼ばれる職業において、とりわけ税理士事務所、社会保険労務士事務所は、経営者の経営相談に直接対応する機会が多い職種であると思います。

税理士にも経営コンサルティングの知識が求められている
特に税理士は、税務だけでなく、売り上げや利益の目標数字の決定など、経営計画そのものである数字に関わります。
経営計画の中では、経営者は売り上げや経費などの数値計画を立てます。
3年や5年先の数値目標をどう設定するべきか。必要な経費項目の数字はどうなるのか。
たとえば、事業拡大のために新しく新社屋を建てるにはどのくらいの資金が必要になるのか、それに伴う人員増員時の人件費はいくら必要になるのかなど、数字として明確にする必要があります。
そこで、本来は「税の申告」など税務業務が本業であるはずの税理士に、経営計画について相談をします。
この時に経営者が税理士に求めるものは、税務のプロとしてのスキルではなくて、経営コンサルティングのスキルになります。
文:ランチェスター社労士 川端康浩
税理士事務所、社会保険労務士事務所、法律事務所など、さまざまな士業の事務所がありますが、顧問を依頼したいときには何を基準にすればよいでしょうか。
今回は士業の事務所の選び方を考えてみます。