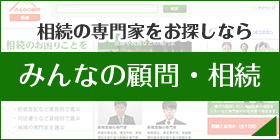弁護士が語る本音!顧問弁護士契約で費用倒れする企業と利益を出す企業の違い

目次
1 はじめに:弁護士から見た顧問契約の「理想」と「現実」
「顧問弁護士をつけているが、実際にはあまり相談していない」「毎月顧問料を払っているものの、得をしているのか分からない」という話を企業経営者の方から聞くことは、実は珍しくありません。
一方で、弁護士の立場からすると、「もう少し早く相談してもらえれば、ここまで大きな問題にはならなかったはずだ」と感じる場面も数多くあります。顧問弁護士契約は、本来、問題が起きてから対応するためのものではなく、トラブルが深刻化する前に弁護士が介入して、経営上の判断を法的に支えるための制度です。
しかし現実には、顧問契約が「何かあったときの保険」や「訴訟になった場合の窓口」としてしか認識されていないケースも少なくありません。その結果、顧問料を支払っているにもかかわらず十分な活用がなされず、「費用倒れだった」という印象を抱いてしまう企業と、顧問契約を通じて確実に経営上の利益を得ている企業との間に、明確な差が生まれています。
そこで、本コラムでは、顧問契約の実情と、その差が生じる理由について率直に解説していきます。
2 顧問料の相場:顧問料(月額)の裏側:何時間分の相談が含まれているのか?追加費用が発生しやすいケースは?
顧問弁護士の月額顧問料は、一般的には数万円から10万円程度に設定されることが多く、中でも5万円程度が最も多いといわれています。最近では、中小零細企業をターゲットとして、より低額な金額で顧問を引き受ける弁護士も存在します。
しかし、金額だけを見て、顧問料が高いか安いかを判断することはできません。本当に重要なのは、その顧問料にどこまでの業務が含まれているのかという点です。
多くの顧問契約では、一定時間までの法律相談や、簡易的な契約書チェック、電話やメールによる助言などが顧問料の範囲内とされています。
一方で、それを超える作業量や専門的な業務については、別途報酬が発生することが一般的です。たとえば、契約書を一から作成したり、大幅な修正を行ったりする場合、あるいは内容証明郵便の作成や交渉、訴訟対応などについては、顧問契約とは切り離して報酬が設定されることが多くなります。
顧問契約をめぐる不満の背景には、「顧問なのだから何でも無料で対応してもらえるはずだ」という誤解があることも少なくありません。顧問契約を結ぶ際には、顧問料の中に含まれるサービスの範囲と、追加費用が発生する場面について、具体的に説明を受け、納得したうえで契約することが不可欠です。
3 顧問弁護士の活用法:弁護士を「使いこなしている企業」と「宝の持ち腐れ企業」の違い
顧問弁護士契約の価値は、契約書の文言以上に、その使い方によって大きく左右されます。弁護士を有効に活用できている企業と、そうでない企業との差は、「相談のタイミング」に現れるといえます。
3-1 成功例:トラブルになる前の予防法務に活用し、早期対応でコストを削減
顧問弁護士を上手に活用している企業の多くは、「まだ問題とまでは言えない段階」で気軽に弁護士に相談を行っています。たとえば、取引先との関係に違和感を覚えたときや、従業員との間でトラブルの芽が見え始めたとき、新しい契約を結ぶ前の段階など、早い時点で弁護士に意見を求めます。
このような早い段階での相談は、比較的短時間で済むことが多く、顧問料の範囲内で対応可能なケースも少なくありません。その上、顧問弁護士からのアドバイスによって、後に訴訟や深刻な紛争へと発展することを防ぐことも可能です。結果として、大きなトラブルに伴う時間的・金銭的なコストを削減でき、顧問契約が有効に機能するといえます。
3-2 失敗例:訴訟などのスポット案件だけ依頼し、契約のメリットを享受できていない
これに対し、顧問契約を結んでいるにもかかわらず、ほとんど顧問弁護士に相談をしない企業も存在します。問題が表面化し、もはや紛争が避けられない段階になってから初めて弁護士に連絡するのです。このような場合、顧問契約の範囲内でできることは限られており、別途費用が必要な業務ばかりとなります。
弁護士としても、早い段階で事情を把握できていれば可能だったはずの対応が、すでにできない状態となっていることも少なくありません。そのことを告げると、企業側が「顧問料を払ってきた意味がなかった」という印象を持ってしまうことになりがちです。
4 顧問弁護士に選ばれる企業像:顧問弁護士が依頼企業に求めること
弁護士の顧問契約は、企業が一方的にサービスを受ける関係ではありません。弁護士の側も、長期的に信頼関係を築ける企業と仕事をしたいと考えています。
弁護士にとって仕事がしやすいと感じるのは、事実関係を正確かつ早めに共有してくれる企業です。また、法的なリスクについて指摘した際に感情的に反発せずに、経営判断の材料として受け止めてくれる姿勢を持ってくれる企業は、弁護士も対応がしやすいといえます。
無理な要求をしてきたり、法的にグレーな対応を当然に要求してくる企業よりも、コンプライアンスを重視する企業の方が、弁護士はより踏み込んだ助言を行いやすいのです。
このような関係性が築ける企業では、弁護士は単なる相談対応にとどまらず、企業のビジネスモデルや業界特性を踏まえた実践的なアドバイスを提供することが可能になります。後から振り返って「大きなトラブルにならなくて済んだ」ということが積み重なり、企業側にとっても大きな利益となります。
5 まとめ:顧問契約を成功させるための具体的なチェックリスト
顧問弁護士契約を「費用倒れ」に終わらせず、実質的な利益につなげるためには、形式的に契約を結んでいるだけになっていないかを定期的に点検することが重要です。以下の視点から、自社の顧問契約を一度振り返ってみると、活用のヒントが見えてきます。
5-1 ポイント①:顧問料に含まれる業務内容は何か
まず、自社が支払っている顧問料に含まれる業務内容を、経営者や担当者が正確に把握しているかを確認する必要があります。相談できる時間の目安や、どこからが追加費用になるのかを曖昧なままにしていると、「想定外の請求が来た」「こんなことまで別料金だとは思わなかった」という不満につながりがちです。顧問契約の範囲を明確に理解しているかどうかは、最初に確認すべき重要なポイントです。
5-2 ポイント②:早い段階で弁護士に相談できているか
次に、問題が深刻化する前の段階で弁護士に相談できているかを振り返ってみてください。取引先との関係で小さな違和感を覚えたときや、従業員への対応で迷いが生じたときなど、まだ紛争化していない段階で相談できている企業ほど、顧問契約の恩恵を受けやすくなります。逆に、事態がこじれてからしか連絡していない場合、顧問契約を十分に活かせていない可能性があります。
5-3 ポイント③:会社の事情を共有できているか
また、顧問弁護士に対して、自社の事業内容や業界特性、経営方針を日頃から共有できているかも重要なチェックポイントです。事情をよく理解してもらえていない状態では、弁護士の助言も一般論にとどまりがちになります。継続的な情報共有がなされていれば、より踏み込んだ、実務に即したアドバイスを受けやすくなります。
5-4 ポイント④:弁護士にどのような役割を期待しているか
さらに、弁護士を「いざというときに使う外部業者」としてではなく、「経営判断を支えるパートナー」として扱えているかも見直すべき点です。法的リスクを指摘された際に、それを単なるブレーキと受け取るのではなく、経営判断の材料として活用できているかどうかが、顧問契約の価値を大きく左右します。
5-5 ポイント⑤:顧問契約の目的は明確か
最後に、顧問契約の目的が明確になっているかも確認が必要です。訴訟対応のためなのか、労務トラブルの予防なのか、契約管理を強化したいのか。目的が曖昧なままでは、顧問契約はどうしても形骸化しやすくなります。自社が顧問弁護士に何を期待しているのかを言語化できているかどうかは、成功している企業とそうでない企業を分ける大きな分岐点です。
5-6 総括
顧問弁護士契約は、結んだだけで自動的に効果が出るものではありません。これらの点をひとつずつ確認し、必要に応じて関係性や活用方法を見直すことで、顧問契約は単なる会社の「コスト」ではなく「経営を支える有効な投資」になるといえるでしょう。
顧問弁護士活用に関する記事はこちら
弁護士顧問契約を「有益な投資」に変えるために知っておくべき4つの視点
弁護士と顧問契約(顧問弁護士)をするタイミングやメリットについて弁護士が解説
【顧問弁護士選択のポイント】、顧問の決定前にやってはいけないことや避けるべき弁護士の特徴について