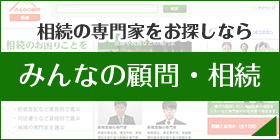弁護士顧問契約を「有益な投資」に変えるために知っておくべき4つの視点
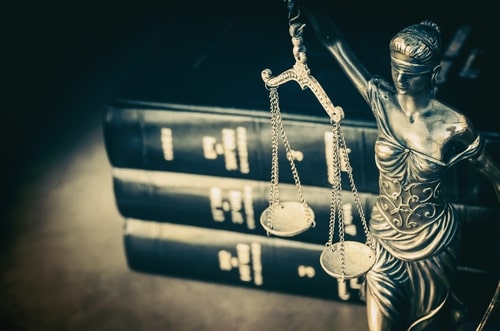
月々の顧問料が発生する弁護士との顧問契約は、「コスト」として捉えられがちです。
ですが、単なる「保険」ではなく、企業経営の意思決定を支えるパートナーとして弁護士を活用すれば、顧問契約は「有益な投資」へと変わります。
この記事では、顧問契約の価値を最大化し、企業の成長に資するものとするための4つの視点を紹介します。
目次
導入 なぜ「顧問契約=コスト」と捉えがちか
「弁護士の顧問契約は、本当に必要なのだろうか」
このように感じる経営者は少なくありません。
多くの企業が弁護士顧問契約を"コスト"と感じてしまう背景には、実は構造的な要因があります。
固定費という心理的ハードル
顧問契約では、一般的に月額3万円から5万円程度の定額報酬が発生します。この金額自体は、企業規模によって重くも軽くもなりますが、問題は「毎月確実に出ていくお金」という性質にあります。
特に目立った法的トラブルがない月でも支払いは続きます。明確な業務の成果が見えないと、「払うだけ損をしているのでは」という気持ちになるのは、ある意味自然な反応といえるでしょう。
平時には価値が見えにくい
企業の経営者や担当者の多くは、トラブルが発生して初めて、「弁護士がいてよかった」と実感します。
しかし、逆に言えば、トラブルが発生していない平時には、弁護士の「ありがたみ」が見えづらいのです。何も問題が起きていない状態は、それ自体が弁護士による予防的助言の成果かもしれません。
けれども、「起こらなかった問題」の価値は、数字で測ることができません。費用対効果が不明瞭に映ってしまうのは、この「見えない成果」が評価しにくいためです。
報酬体系や姿勢への不信感
さらに、弁護士に対する不信感が「コスト」という認識を強めているケースも少なくありません。
報酬体系が不透明だったり、説明が不十分だったりすると、「本当に必要な作業なのだろうか」「無駄にタイムチャージを付けられているのでは」という疑念が生まれます。
また、曖昧な物言いばかりで明確な結論を示さない、質問に対して「ケースバイケースです」としか答えないなどといった対応に不満を感じる経営者も多いでしょう。
弁護士との間に信頼関係が築けていないケースでは、「コスト感」がより強まります。「この人は本当に自社のことを考えてくれているのか」という疑問が頭をよぎるたびに、毎月の顧問料が重く感じられるようになるのです。
POINT1 「顧問弁護士のメリット」日常相談をカバーしてリスクを未然に防ぐ
ここからは、顧問契約の価値を最大化するための具体的な視点を見ていきましょう。
顧問弁護士の最大の役割は、リスクの「火種」を早期に把握し、トラブルになる前に潰すことにあります。
気軽に相談できる安心感
顧問契約があることで、ちょっとした疑問や違和感も気軽に相談できる環境が整います。
たとえば、「取引先から届いた契約書に、少し気になる条項がある」「退職した社員が妙なことを言っていたんだけど、これって大丈夫かな」といった、まだ問題化していない段階での"モヤモヤ"を相談できるのは、顧問契約ならではのメリットです。
初動が早ければ、それだけ解決もスムーズになります。選択肢も多く、コストも時間も最小限で済みます。この「気軽に相談できる」という心理的な障壁の低さこそが、顧問契約の隠れた大きな価値なのです。
企業理解に基づく的確な助言
顧問弁護士は、企業との長期的な関係を通じて、事業内容や内部事情、さらには経営者の考え方や判断の傾向まで深く理解していきます。
これは、スポット(単発)で依頼する弁護士との決定的な違いです。スポットの場合、毎回ゼロから事情を説明しなければなりません。「うちの業界ではこういう商習慣があって……」「以前こんなトラブルがあったんですが……」といった背景説明に多くの時間を費やすことになります。
一方、顧問弁護士であれば、こうした前提を共有した状態でスタートできます。過去の案件との関連性も踏まえて、「前回のケースと同じように対応するなら、今回はこういう点に注意が必要です」といった一貫性のある実務的なアドバイスが可能となります。
また、経営者の価値観を理解しているからこそ、その会社に最適化した助言ができます。法律的に正しいだけでなく、「その会社にとって現実的かどうか」という視点でのアドバイスは、長期的な関係があってこそ実現するものです。
リスクの早期発見と対応
トラブルが表面化する前の段階で適切に対応することで、社内外の問題を拡大させずに収束させることも可能です。
「小さな違和感」の段階で相談し、適切な手を打つ。これが、顧問弁護士による予防法務の真骨頂です。病気で言えば、定期健診で早期発見するようなものです。早ければ早いほど、治療は簡単で、費用も安く、完治の可能性も高くなります。
POINT2 社長の意思決定を支える「弁護士顧問契約の対応範囲の明確化」
顧問契約を価値あるものにするには、曖昧なまま契約せず、「どこまで」「いくらで」対応してもらえるのか、明確にしておく必要があります。
これは、弁護士に対する不信感を防ぐためだけでなく、予期せぬ出費を防ぎ、弁護士のサポートを最大限に活用するために不可欠です。
顧問料でカバーされる範囲の確認
まず押さえておくべきは、「月額の顧問料で何がカバーされるのか」という点です。これは法律事務所によって、また契約内容によって大きく異なります。
一般的には、以下のような業務が顧問料に含まれることが多いでしょう。
- 日常的な法律相談:電話やメールでの相談、簡単な法的見解の提示
- 簡易な書類のレビュー:契約書の簡単なチェック(大規模・複雑なものを除く)
- 内容証明郵便などの簡単な文書作成:数ページ程度の文書作成
ここで重要なのは、「簡単な」「日常的な」といった言葉の定義が、弁護士と依頼者で異なることがある点です。契約前に、具体例を挙げながら、どこまでが顧問料の範囲に含まれるのかを明確にしておきましょう。
報酬体系の理解
別途費用が発生する場合の報酬体系には、主に以下の種類があります。どの体系が適用されるかを事前に確認し、納得した上で依頼することが重要です。
- 着手金・成功報酬:事件依頼時に着手金を支払い、事件終了後にその成功の度合いに応じて成功報酬を支払う方式
- タイムチャージ:弁護士が業務に費やした時間に基づいて報酬を支払う方式
特にタイムチャージでは、上限金額の設定や、想定時間をすり合わせておくと安心です。
意思決定の質を高める「情報」の価値
ここまで、費用の話を中心にしてきましたが、顧問料の本質的なリターンは「情報」にあります。
顧問弁護士は、法的知識や過去の事例の経験から「将来の見通し」を示してくれます。これは、経営判断の質を大きく左右する重要な情報です。具体的には、紛争の勝率や、賠償見込み、解決までの期間やコストなどの見通しなどが挙げられるでしょう。
こうした情報があれば、経営者は「徹底的に争うべきか、早期に和解すべきか」という重要な意思決定を、合理的な判断に基づいて行えます。その結果、大きな損失を回避したり、無駄なコストをかけずに済んだりするでしょう。
POINT3 業界/取引形態に強い弁護士の選び方
現代の企業法務は多様化・複雑化しており、一人の弁護士が全ての分野を網羅するのは困難です。医療の世界に内科・外科・眼科といった専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。
そのため、自社の事業内容や直面する課題に合った専門性を持つ弁護士を選ぶことが、投資効果を高めることになります。
相談内容に応じた弁護士像の使い分け
弁護士への依頼は、内容によって求める専門性が異なります。すべてを一人の弁護士に頼る必要はなく、相談内容に応じて使い分ける柔軟性が重要です。
■一般法律相談
日常的な法務相談においては、過度な専門性より、コストとのバランスを重視することも一つの考え方です。一定の品質を備え、幅広い対応が可能な弁護士を選ぶことで、実務上のニーズに効率的に対応できるケースもあります。
■専門法律相談
M&A、知的財産、特殊な紛争案件など、高度な専門性が求められる場合は、品質を最優先すべきです。その分野での影響力や知見が豊富な専門家を選びましょう。法律雑誌への寄稿や書籍の著者、判決での代理人情報、他社の法務部門からの口コミなどが選定の有力な手がかりとなります。
弁護士の探し方と選定方法
では、実際に弁護士を探す際には、どのようにすればよいのでしょうか。従来は人づてに紹介してもらうのが一般的でしたが、現在はより効率的な方法もあります。
■プラットフォームの活用
近年では、オンラインの弁護士アクセスプラットフォームも登場しており、自社のニーズに合った弁護士を手軽に探すことができます。複数の弁護士から回答を得て、比較検討することも可能です。
■選定プロセスの透明化
候補者を選定する際には、複数の法律事務所から提案書を提出してもらい、内容を比較評価する「プロポーザル方式」が有効です。これにより、価格だけでなく、技術力や業務遂行体制なども含めて総合的に判断でき、選定プロセスの透明性も確保できます。
POINT4 契約後の“活かし方”=社内活用の仕組みづくり
優れた弁護士と契約しても、社内に活用する仕組みがなければ宝の持ち腐れになってしまいます。顧問弁護士を最大限に活用し、投資効果を高めるためのポイントは以下の通りです。
主体的な関与と明確な依頼
弁護士に「丸投げ」するのではなく、案件の背景や自社の目的を丁寧に説明し、ゴールを共有することで、弁護士の対応も精度が上がります。
また、日頃から自社の戦略や社風、経営者の考え方を共有し、信頼関係を築いておくことも重要です。「この会社はスピード重視で、多少のリスクは取る方針」「この社長は慎重派で、リスクは最小限に抑えたい」といった特性を理解していれば、弁護士も適切な助言ができます。
社内での役割分担の意識
外部の弁護士と社内の担当者・経営者の役割を明確に分けることも、効果的な活用のカギとなります。
外部の弁護士は、法律の専門家ではありますが、事業内容を必ずしも熟知しているわけではありません。そのため、考えられるあらゆるリスクを網羅的に指摘する傾向があります。
しかし、すべてのリスクを完全に排除しようとすれば、新規事業など始められません。ビジネスとは、本質的にリスクを取る行為だからです。
ここで必要になるのが、社内の担当者や経営者による「取捨選択」です。弁護士が指摘したリスクに対して、ビジネス上のインパクトや、対策のコストといった視点から判断します。
この役割分担を明確にしておけば、弁護士の意見に振り回されることなく、かといって無視することもなく、バランスの取れた判断ができます。
定期的なコミュニケーションの仕組み化
会社の成長段階に合わせて、弁護士との関わり方も変化させる必要があります。創業期と成長期、さらに成熟期では、直面する法的課題も異なるからです。
事業が拡大し、法律相談の内容も多様化してきたら、より頻繁にコンタクトを取り、相談しやすい関係を維持することが大切です。
セカンドオピニオンの活用
重要な経営判断の際には、一人の顧問弁護士の意見に固執せず、他の弁護士からセカンドオピニオンを得ることも検討しましょう。これにより、状況を多角的に分析し、より冷静で客観的な判断を下すことができます。
まとめ「弁護士の顧問契約をコスト」ではなく有益な投資に変えるために
弁護士との顧問契約は、単に月々の費用を支払う「コスト」ではありません。企業の現状と将来の成長を見据え、適切な弁護士をパートナーとして選び、主体的に活用することで、リスクを管理し、経営判断の質を高め、事業の成長を加速させるための「有益な投資」となります。
「どの弁護士とどう付き合うか」で、顧問契約の価値は大きく変わる。その視点を持つことが、最初の一歩です。
顧問弁護士活用に関する記事はこちら
弁護士が語る本音!顧問弁護士契約で費用倒れする企業と利益を出す企業の違い
弁護士と顧問契約(顧問弁護士)をするタイミングやメリットについて弁護士が解説
【顧問弁護士選択のポイント】、顧問の決定前にやってはいけないことや避けるべき弁護士の特徴について