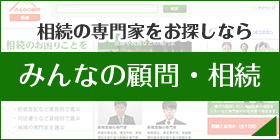【休廃業・解散】黒字廃業は意外に多い?高齢代表者の現状もあわせて解説

日本にある会社の99.7%は中小企業と言われており、家族経営の企業も少なくありません。人口減少が進む今、会社経営者層の高齢化も進んでおり、会社の廃業・解散も増加傾向にあります。
業績が好調な会社なら「事業承継」も選択肢の1つですが、後継者不足に悩まされた結果、黒字廃業を決断するケースも多くなっています。そこで、本記事では会社の休廃業・解散について、黒字廃業や高齢代表者の現状にも触れながら詳しく解説します。
目次
日本の会社が抱える課題|黒字廃業は意外に多く、赤字廃業の比率も上昇
円安進行や少子高齢化など、日本の会社が抱える課題は多岐にわたっており、経営努力を重ねた結果「廃業」を選択する会社は決して少なくありません。廃業と聞くと、多くの人が業績不振による解散や倒産をイメージするかもしれません。
しかし、実際には黒字廃業も多く、後継者不足の影響も伺えます。この章では東京商工リサーチのデータを基に、日本企業が直面する黒字廃業・赤字廃業について詳細を解説します。
参考URL 株式会社東京商工リサーチ 「2024年の「休廃業・解散」企業、過去最多の6.26万件 高齢代表者の退出が加速、赤字率は過去最悪に」
黒字廃業は意外と多いが減少傾向
東京商工リサーチの調査によると、2024年の休廃業・解散企業は過去最多の6万2,695件に達しました。このうち、直前の決算が黒字だった企業の割合は51.5%と過半数を占めています。これまでの調査でも黒字廃業率は高く、利益がしっかりと出ている会社でも、やむを得ず廃業に至っていることがうかがえます。
黒字廃業の背景には後継者不足や将来への不安から、業績が良い段階で会社を清算し、手元に資金を残したいという経営者の判断があります。
赤字企業の割合も48.5%と過去最悪を更新
同統計では、赤字企業の割合も48.5%と過去最悪を記録しています。人件費や原材料費の高騰、円安進行による金利上昇といった厳しい経済環境が原因とみられています。
高齢の代表者が多い企業では、設備投資や新規雇用に踏み切れず、競争力を失う傾向があります。古い体制のままの経営が続き、赤字での廃業に至る「負のスパイラル」が起きていると分析されており、今後は赤字廃業が逆転することも予想されています。
休廃業・解散と経営者の高齢化問題の現状とは
大切な自身の会社を休廃業・解散させるという決断は、そう簡単にはできないものです。特に数代にわたって看板を受け継いでいるような会社なら、自身の決断でその歴史を閉じることになってしまいます。しかし、高齢の経営者が経営を続けることにはリスクも多く、十分な注意が必要です。
休廃業・解散のメリットとデメリット
会社の休廃業や解散は、事業の終わりを意味しますが、すべての経営者にとってネガティブな選択肢とは限りません。メリットとデメリットを正しく理解し、自身の状況に合った決断を下すことが重要です。
①メリット
- 経営者個人の新たな人生がスタートできる
- 手元に資金を残せる
- 株式や事業用固定資産を整理することで相続のリスクを大きく減らせる
- 経営ストレスから解放される
②デメリット
- 従業員の雇用喪失
- 取引先や顧客との関係終了
- 複雑な手続きと費用
- 借金が残されるリスクがある
経営者が高齢化している3つのリスク
経営者が高齢化していることも多い今、会社にとって単なる世代交代の問題にとどまらず、事業の継続を脅かすさまざまなリスクを引き起こしています。
1.事業承継のリスク
まず、多くの高齢経営者が悩んでいるのは「事業承継」です。家族経営の場合は子や孫に次の代を任せたいと考える傾向がありますが、すでに独立していたり、子や孫がいなかったりする方もいます。経験やノウハウを持つ後継者も見つからず、育成が間に合わない場合も多くなっています。
2.会社の衰退
さらに、高齢の経営者は、新たな設備投資や技術革新などに慎重になる傾向があります。その結果、時代の変化に対応できず、同業他社との競争に敗れて事業が縮小・衰退していくおそれがあります。
3.健康問題
経営者の高齢化は、体調不良や病気といった健康問題のリスクを抱えています。経営者が倒れてしまった場合、事業計画の遅延や重要な意思決定ができなくなるなど、経営自体が立ち行かなくなる可能性があります。
手元資金を残して廃業するという選択
廃業は会社の業績が悪化してからやむなく行うもの、というイメージが一般的かもしれません。しかし、会社が黒字のうちに廃業を決断することは、経営者にとってだけではなく、従業員にとっても非常に賢明な選択となり得ます。
円満な黒字廃業のメリット
業績が好調な時期に廃業することで、会社を清算する際に残った資産(現金、不動産など)を、老後の資産として確保できます。赤字が続き、借入金が増大した状態で廃業を決断した場合、会社の資産だけでは負債を完済できなくなります。会社と経営者の破産に至ることも少なくありません。
廃業は計画的に進めることが多く、従業員の生活を守るために類似業種へ紹介したり、技術の承継を行うことも可能です。円満な黒字廃業は長年の経営努力の集大成として、経営者と従業員の生活を守るための戦略的な決断と言えるでしょう。
廃業の相談は誰にする?
廃業は会社の清算手続きや税務処理だけではなく、従業員の雇用問題など、専門知識を要します。経営者一人で進めることは難しいため、専門家のサポートが不可欠です。では、誰に相談するとよいのでしょうか。
商工会議所・金融機関など
廃業の相談窓口として、商工会議所や信用保証協会、取引のある金融機関は廃業や事業承継に関する相談に応じています。まずはこうした身近な窓口に相談し、情報を集めてみるのも良いでしょう。商工会議所には「経営安定特別相談室」が設けられており、迅速に指導・助言を行ってくれます。
よろず支援拠点
「よろず支援拠点」とは中小企業などが抱える、経営上のさまざまな悩みに無料相談で対応している公的機関です。廃業についても対応しており、最寄りの各都道府県に窓口の利用が可能です。電話、メール、FAX等で相談予約ができます。
参考URL よろず支援拠点
都道府県等中小企業支援センター
中小企業庁が各都道府県に設置している公的な相談窓口である「都道府県等中小企業支援センター」も廃業などの相談が可能です。
中小企業の経営に関するあらゆる相談を無料で受け付けており、廃業や事業承継に関する専門家が常駐しています。資金繰りや事業再生など経営全般の悩みを聞き、事業診断を行ってくれるため安定経営を目指す際の利用もおすすめです。民間企業や士業との連携も行っています。
各エリアのセンターは、以下からご確認ください。
参考URL 中小企業庁 都道府県等中小企業支援センター等
士業などの専門家
弁護士・税理士・司法書士といった士業は法律の専門家として廃業や会社の事業承継、清算業務について対応しています。
たとえば税理士の場合、現在の資産状況に合わせ、解散に向けた税務処理や相続・事業承継も見据えた清算サポートが可能です。経営コンサルタントも交えて、長期的な廃業計画を策定するケースもあります。
弁護士は労働問題や債務の整理なども見据えた廃業・清算に深く対応可能です。やむを得ず民事再生や破産に至った際も継続して相談できます。会社の登記など司法書士と連携するケースも少なくありません。中小企業診断士と連携する場合もあります。
廃業は複数の士業や専門家が連携しサポートすることが多く、まずは相談してみることがおすすめです。
まとめ
事業の休廃業や解散は、必ずしもネガティブな選択肢ではありません。特に、黒字のうちに廃業を決断することは、経営者だけではなく従業員の生活を守る効果もあります。
経営者の高齢化による後継者不足や経済動向により、赤字廃業の比率も増加傾向にあります。破産リスクを回避するためにも、まずは早期に専門家へ相談を開始することがおすすめです。
経営者一人で抱え込まず、税理士や弁護士、司法書士といった専門家や、商工会議所、中小企業支援センターなどの公的機関に相談を始めてみてはいかがでしょうか。