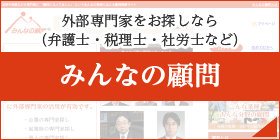相続開始で知っておきたい【相続開始日・起算点はいつなのか】について弁護士が解説

相続手続きは、人生の中でもそう何度も経験することではありません。
多くの方にとって、相続は突然の出来事です。そのため、親族の誰かが亡くなったとき「相続はいつから始まるのか?」「手続きの期限はいつから数えるのか?」といった基本的な疑問を持つ方が少なくありません。
実は、相続には「開始日」と呼ばれる明確な起点があり、そこから数えて各種手続きに関する期限が動き出します。しかし、その「相続開始日」は、亡くなり方や確認方法によって微妙に異なることもあります。
そこで、今回は、相続開始日の基本から、起算点となるタイミング、注意すべき例外的なケース、そして早期に専門家へ相談するメリットまで、詳しく解説します。
目次
1 相続開始日はいつなのか?
相続が発生する「起点」は、法律上明確に定められています。民法882条によると、相続は「被相続人の死亡によって開始する」と規定されています。つまり、亡くなった日が相続開始日となります。ただし、「死亡」と一口に言っても、実際にはいくつかのパターンがあります。
1-1 自然死亡のケース
最も多いのが、自然死亡(病死や老衰、事故死など)のケースです。この場合、医師によって死亡が確認された時刻(死亡診断書に記載された死亡時刻)が相続開始日となります。戸籍上にもその日時が記載され、すべての手続きの基準となる起算点となります。
このような自然死の場合、相続人も比較的すぐに死亡の事実を把握できるため、手続きにも移りやすい傾向があります。
1-2 認定死亡のケース(行方不明者の死亡確認)
事故や災害などで遺体が見つからない場合でも、死亡が確実と判断された場合には「認定死亡」とされることがあります。たとえば、東日本大震災などの災害時に多く適用されました。
この場合、医師の診断や当時の状況から死亡したと認定された日付が、相続開始日になります。戸籍上もその日が死亡日として記載されます。
1-3 擬制死亡のケース(失踪宣告)
もっとも注意が必要なのが「擬制死亡」、すなわち失踪宣告による死亡扱いのケースです。
たとえば、長期間行方不明になっている人に対し、家族が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てた結果、「死亡とみなす」判断が下されることがあります。失踪宣告には以下の2つの種類があります。
- 普通失踪:7年以上生死不明の場合
- 特別失踪:戦争・船舶事故・震災などの危難に巻き込まれ、1年間生死不明の場合
このようなケースでは、家庭裁判所が死亡とみなす日、すなわち法律上の死亡日(失踪期間の満了日)が相続開始日になります。なお、宣告が出された日ではない点に注意が必要です。
2 期限のある相続手続期限の起算点はいつ?
相続に関する手続きには、「いつまでにやらなければならない」という期限がいくつか法律で定められています。これらの期限は、基本的に、相続開始日を起算点としてカウントされます。
主な期限付き手続きと起算点は、以下のとおりです。
- 相続放棄・限定承認の申述:相続開始を知った日から3か月以内
- 相続税の申告・納付:相続開始日から10か月以内
- 準確定申告(被相続人が個人事業主の場合):相続開始日から4か月以内
ここで注意すべきなのは、「相続放棄・限定承認」は例外的に「相続開始を知った日」が起算点になるという点です。相続税申告や準確定申告などその他の手続は、いずれも相続開始日が起算点となります。
なお、相続手続きの期限については、下記のリンクをご参照ください。
「相続手続きの流れ」
3 相続開始日と相続開始を知った日に差があるケース
通常は、相続人がすぐに死亡の事実を知るケースが多いのですが、以下のように「死亡していたが、それを知ったのは後日だった」という例もあります。
例えば、①疎遠になっていた親族が数か月前に亡くなっていたことを、自治体からの通知や新聞で知ったというケースや、②被相続人が外国に居住しており、現地の事情で訃報が遅れたというケースでは、相続放棄・限定承認の起算点は、被相続人が亡くなっていたことを知った日から数えることとなります。
裁判例では、「相続開始を知った日」とは、法律的には「被相続人の死亡と、自分が相続人であることの両方を知った日」を意味するとされています。したがって、「単に死亡の噂を聞いた」という程度では足りず、客観的に死亡が確認された日が基準になるとする裁判例が多数見られます。
ただし、「最近になって死亡を知った」と主張しても、実際の死亡時から長く何も手続きを取らずにいた場合には、「実際にはもっと前から死亡を知っていた」と裁判所に判断される可能性があります。
こうした誤解を避けるためにも、通知を受け取った日や死亡を知った経緯を証明できる資料(たとえば、手紙・新聞記事・メールなど)を残しておくことが大切です。
4 相続手続きは早めに専門家に相談しましょう
相続手続きは、単に財産を引き継ぐという作業にとどまりません。
借金を引き継がないための「相続放棄」や、財産の分け方を決める「遺産分割」、税金の申告・納付、名義変更のための登記など、さまざまな手続きがあります。これらは法律や税金のルールが複雑に関係しているため、間違った判断をしてしまうと、あとになって多額の税金を払うことになったり、相続人同士で争いが起きたりするなど、大きな問題に発展するおそれがあります。
特に次のようなケースでは、早めに弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
- 相続人の一部と疎遠で、連絡が取りにくい
- 借金や保証債務など、マイナスの財産があるかもしれない
- 遺言書が見つかったが、内容に疑問がある
- 相続税の納税や延納に関する対応が必要
- 生前贈与や養子縁組があった
専門家であれば、相続開始日や起算点を正しく整理しながら、各種の期限に間に合うよう対応方針を提案することができます。
弁護士は、遺産分割の交渉や調停、相続放棄の申述代理、遺言の有効性の判断、そして相続トラブルの予防と解決に関して、総合的に対応することができます。税金の問題が絡む場合には、税理士との連携も重要です。
「いつからが相続がスタートするのか」「何をいつまでにやる必要があるのか」ということがわからない方は、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。安心かつ確実に対応していくことが可能です。
【関連記事】こちらもお読みください