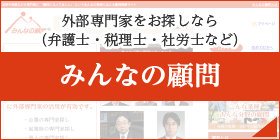【個人事業主・自営業者が死亡した場合の相続手続き】特有の問題や屋号の承継等について解説

個人で飲食店やサービス業、フリーランスとして活躍していた方が亡くなった場合、その相続手続きには“事業特有”の対応が求められます。
たとえば、屋号の扱いや事業資産・負債の整理、青色申告の対応など、通常の相続とは異なる注意点が数多く存在します。
この記事では、個人事業主・自営業者が亡くなった際に生じる相続手続きについて、事業の「継続」「廃止」それぞれのパターンに応じて必要な手続きをわかりやすく解説します。
目次
個人事業主・自営業者特有の問題・注意点
個人で事業を営んでいた方が亡くなった場合、その相続手続きは、いわゆる「会社員」のものとは性質が大きく異なります。なぜなら、事業に紐づく資産や契約関係、税務手続など、事業特有の処理が発生するからです。ここでは、個人事業主・自営業者に特有の注意点を3つに分けて整理します。
廃業・再開業に関する届出が必要になる
個人事業主の方が亡くなったあとは、事業を「やめるか」「引き継ぐか」の判断が必要になります。そして、この判断に応じて、所定の手続きを行うことが求められます。
まず、事業をやめる場合には、税務署に「廃業届出書」を提出する必要があります。これを出さずに放置しておくと、税務上は事業が継続しているものと扱われてしまうため注意が必要です。
一方で、家族などが事業を引き継ぐ場合には、今度は相続人が新たな事業主として「開業届出書」を提出することになります。事業の内容や所在地に変更がある場合には、その旨の記載も必要です。
このように、「廃業するのか、引き継ぐのか」という選択は、単なる方針決定にとどまらず、相続手続き全体の流れにも大きく影響します。できるだけ早めに方向性を決めておくことが、手続きをスムーズに行うためのカギとなります。
事業に関わる財産と負債を把握する必要がある
個人事業主が亡くなると、その方の生活に関わる財産だけでなく、事業に関する財産や借金も相続の対象になります。たとえば、店舗・設備・商品在庫・営業用の車・売掛金などは事業用の「資産」として考えられますし、借入金や買掛金などの「負債」も当然ながら相続対象に含まれます。
このように、事業と生活の資産が混在しているのが、個人事業主の相続の特徴です。遺産の全体像を把握するには、帳簿や通帳、契約書などを確認して、どれが事業用かを一つずつ丁寧に仕分けていく必要があります。
また、事業が順調に見えていても、思いがけず大きな負債が残っているケースもあります。そういったリスクを見落とさないためにも、早い段階で資産と負債の内容を洗い出し、必要に応じて相続放棄や限定承認といった選択肢も視野に入れておくことが大切です。
準確定申告の義務がある
個人事業主の方が亡くなると、相続人には「準確定申告」という特有の手続きが発生します。これは、亡くなった方の最後の年の所得について、相続人が代わりに税務署へ申告・納税を行う制度です。
具体的には、被相続人が亡くなった日までの収入や経費を整理し、通常の確定申告と同じような内容で申告書を作成します。提出期限は、「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」と決まっており、比較的タイトなスケジュールです。
とくに個人事業を営んでいた場合、売上や経費の計算、帳簿の整理などが必要になるため、申告作業が煩雑になりがちです。放置してしまうと延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性もあるため、できるだけ早めに専門家と連携し、対応の段取りを整えることが大切です。
相続人が事業を引き継ぐ場合の手続き
個人事業主の方が亡くなったあと、その事業を相続人が引き継ぐ場合は、「廃業」ではなく「新たな開業」として、いくつかの届出や申請が必要になります。
以下では、主な届出の内容と提出期限を紹介します。
個人事業の開業届を提出する
まず必要なのが、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出です。たとえ被相続人の事業をそっくり引き継ぐ場合でも、相続人自身は個人事業・自営業を開業することになるため、この手続きは必須です。
提出先は相続人の住所地を管轄する税務署で、提出期限は原則として「被相続人が亡くなってから1か月以内」となっています。
青色申告をするなら、承認申請書の提出を忘れずに
被相続人が青色申告を行っていた場合でも、その青色申告の効力は相続人には引き継がれません。相続人も引き続き青色申告による優遇措置を受けたい場合は、「青色申告承認申請書」をあらためて提出する必要があります。
この申請の期限は少し複雑で、被相続人が亡くなった日によって変わります。たとえば、8月末までに亡くなった場合は「死亡日から4か月以内」、年末にかけて亡くなった場合は「年内」または「翌年2月15日まで」など、期間が異なるため注意が必要です。被相続人が白色申告だった場合も別の期限が定められているため、事前に確認しておきましょう。
青色専従者給与を出すなら、届出を
事業を手伝ってくれる家族に給与を支払う場合、特に青色申告を行うのであれば、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」も必要です。この届出を出さないと、家族に払った給与が経費として認められない可能性があります。
提出期限は原則「その年の3月15日まで」、ただし1月16日以降に事業を始めた場合などは「開業日から2か月以内」となっています。
従業員を雇うなら給与支払事務所の届出を
引き継ぐ事業に従業員がいる、あるいは新たに人を雇う予定がある場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。ただし、すでに開業届を出す際に給与支払いの有無を記載している場合は、別途この届出をする必要はありません。
消費税についての注意点
消費税の面では、事業を始めた初年度は原則として課税が免除されます。ただし、大きな設備投資を予定している場合などは、「課税事業者」となることで消費税の還付が受けられる可能性があります。そのためには「消費税課税事業者届出書」など、必要な手続きがいくつかあります。
なお、被相続人が課税事業者だった場合でも、その地位は相続人に自動的に引き継がれるわけではありません。必要に応じて、改めて選択届出を行う必要があります。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
屋号を引き継ぐ方法
相続人が個人事業を引き継ぐにあたり、「屋号」もそのまま使いたいというケースは少なくありません。屋号とは、ビジネス上の「名前」にあたるもので、たとえば飲食店や工務店、美容室などで使われている店舗名やサービス名がそれに該当します。日常的に看板や広告に使われている名称なので、顧客にとっても屋号は事業の“顔”として認識されています。
屋号の使用には、特別な手続きは必要ありません。新たに開業届を出す際、屋号欄に被相続人と同じ名称を記載すれば、そのまま引き継ぐことができます。たとえば、被相続人が「○○商店」という屋号で営業していたのであれば、相続人も同じ「○○商店」を使って開業することが可能です。
ただし、屋号が長年地域に親しまれていたり、信頼やブランド価値が築かれている場合は、それを引き継ぐことによって生じる責任や誤認リスクもあります。トラブルを避けるためにも、旧経営者との関係性や引き継ぎの経緯を丁寧に説明したり、必要に応じて看板や名刺などに「先代から継承」などの一言を添える工夫も有効です。
相続人が事業を廃止する場合の手続き
相続人が被相続人の事業を引き継がず、廃業することを選んだ場合には、いくつかの行政手続きを行う必要があります。個人事業は開業時に税務署などへ各種届出をしているため、廃業の際にも「やめるための手続き」が求められるのです。
以下では、廃業に際して必要となる主な書類と提出期限をまとめました。
個人事業主・自営業者の死亡届出書
まず必要となるのが、事業主の死亡を税務署に知らせる「死亡届出書」です。特に定められた提出期限はありませんが、可能な限り早めに提出しておくことが望ましいとされています。
個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
廃業の基本となる届出です。開業時に提出した書類と同じ様式を使って、今度は廃業の内容を記入し、被相続人が管轄されていた税務署へ提出します。こちらは「死亡日から1か月以内」が目安となっています。
事業廃止届出書(消費税)
被相続人が消費税の課税事業者であった場合には、消費税に関する「事業廃止届出書」も必要です。これにより、消費税課税事業者としての登録を終了させることになります。提出は死亡後すみやかに行うのが原則です。
青色申告の取りやめ届出書
亡くなった事業主が青色申告を行っていた場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。これは、青色申告の継続意思がない(=事業が廃止される)ことを正式に通知するためのものです。提出期限は「死亡の翌年3月15日まで」です。
給与支払事務所等の廃止届
被相続人が従業員を雇っていた場合には、「給与支払事務所等の廃止届」も必要になります。ただし、すでに「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を提出している場合には、これをもって廃止の届出を兼ねることができるため、改めて提出する必要はありません。
専門家に相談
個人事業主の相続は、一般的な相続と比べて判断や手続きが複雑になりがちです。事業を引き継ぐのか、廃業するのか、それによって提出すべき書類も異なりますし、税務上の影響も無視できません。相続税・所得税・消費税などが絡み合うため、自己判断で進めるには限界があります。
たとえば、事業用の資産と私的な財産が混在している場合には、どこまでが相続の対象になるのかを慎重に仕分ける必要があります。さらに、青色申告や専従者給与の扱い、消費税の還付の可否など、専門的な知識が求められる場面も多いでしょう。
こうした場面では、税理士・司法書士・弁護士など、それぞれの分野に強い専門家のサポートを受けることで、手続きのミスや思わぬトラブルを避けることができます。特に「廃業と承継のどちらが適切か」「限定承認や相続放棄を検討すべきか」といった判断が必要な場合は、早めに相談することが重要です。
最初は「何を相談すればよいかわからない」という状態でも問題ありません。状況を整理するためにも、まずは一度、専門家に話をしてみることをおすすめします。
【関連記事】こちらもお読みください