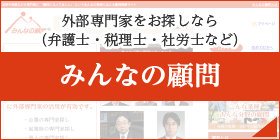先に自分が死んだらペットはどうなる?おひとりさまも安心!ペット信託などの検討。

大切なペットが飼い主よりも長く生きた場合、その後の生活をどうするか考えたことがありますか?ペットは家族の一員ですが、法律上は財産を相続することができません。そのため、飼い主が病気や事故で世話を続けられなくなった場合や、亡くなった後にペットがどうなるのか、事前にしっかり準備しておく必要があります。
この記事では、ペット信託をはじめ、ペットの未来を守るための具体的な方法をご紹介します。
目次
ペットに財産を相続させることはできるのか?
先述の通り、ペットに財産を相続させることは、日本の法律では認められていません。民法では、相続できるのは婚姻関係にある配偶者や血縁関係のある親族だけと定められています。そのため、ペットが直接財産を受け取ることはできません。
しかし、ペットの生活を守る方法はあります。信頼できる人にペットを託し、その人にペットの生活費や世話に必要な資金を預けるのが一般的です。事前にこうした準備をしておくことで、ペットが安心して暮らせる環境を整えることができます。
もし、身近にペットを託せる人がいない場合には、「ペット信託」という制度を利用することも可能です。この制度を使えば、信頼できる第三者にペットの世話をお願いすることができます。
ペットのための信託制度・ペット信託とは
ペット信託とは、飼い主が病気や事故でペットの世話ができなくなったときや、飼い主が亡くなったときに備える仕組みです。
高齢の飼い主は、突然の体調不良や自分がペットより先に亡くなるリスクを抱えています。同居している家族がいればペットを託せますが、家族や知人が近くにいない場合もあります。そんなときに、ペット信託を活用すれば、ペットの世話を誰かにお願いすることができます。
ペット信託の具体的な進め方
ペット信託は「信託契約」という法律に基づいて行われます。信託契約とは、財産を信頼できる人に託して、その目的に沿って管理してもらう契約です。
ペット信託の場合、飼い主(委託者)は、信頼できる第三者(受託者)と契約を結びます。この契約で、ペットの世話に必要な費用を受託者に託します。飼い主が元気なうちは自分でペットの面倒を見ますが、病気やケガで世話ができなくなったとき、契約で決めた受益者がペットの世話を引き継ぎます。
ペット信託の主な関係者は次のとおりです。
- 委託者:ペットの飼い主。信託財産(ペットの飼育費用)を託す人。
- 受託者:信託財産を管理する人。
- 受益者:実際にペットを世話する人。ペット仲間やペット専用の施設などが該当します。
委託者に相続人が存在する場合には、のちの争いを避けるため、ペット信託について記載した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ペット信託を利用すれば、飼い主に万が一のことがあっても、ペットの生活を守る仕組みを作ることができます。大切なペットが安心して暮らせるよう、事前の準備を考えてみましょう。
ペット信託のメリット・デメリット
ペット信託は、ペットのために財産を確保できる便利な仕組みですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
ペット信託のメリット
ペット信託のメリットは、主に以下の3つです。
ペットのために財産を確実に使える
ペット信託を利用すれば、ペットのためだけに使う財産を確保することができます。信託財産は契約で決めた目的以外には使えないため、ペットの飼育費用を確実に残せます。
さらに、信託監督人を選べば、ペットがちゃんと世話されているか確認することもできます。これによって、財産が正しく使われているか、ペットが安心して暮らせているかを第三者にチェックしてもらうことができます。
ペットの生活環境を細かく指定できる
ペット信託は契約内容を柔軟に設定できるため、ペットの生活に合わせた条件を細かく決められます。たとえば、以下のような希望を反映できます。
- かかりつけの獣医や定期健診の指定
- 餌の種類やトリミングの頻度
- 散歩の回数や寝たきりの場合の対応
- ペットの葬儀や埋葬の方法
これらを具体的に決めておくことで、大切なペットが自分の代わりにもしっかりと世話される環境を整えることができます。
ペットの死後の財産も柔軟に引き継げる
ペットが亡くなった後の財産の扱いも、ペット信託なら事前に決めておけます。例えば、残った財産を家族に引き継ぐ、あるいはペットを世話してくれた人に渡すといった選択も可能です。これにより、二次以降の相続についても柔軟に対応できます。
ペット信託は、ペットの生活を守るだけでなく、飼い主の希望を細かく反映できる便利な制度です。
ペット信託のデメリット
ペット信託のデメリットは、主に以下の3つです。
一括で大きな費用が必要
ペット信託では、ペットが亡くなるまでに必要な飼育費用をまとめて準備する必要があります。たとえば、小型犬なら年間20万円程度、大型犬では年間30万円以上かかる場合があります。これにペットの平均寿命を考慮して計算すると、大型犬では数百万円の一括支払いになることもあります。
費用が不足しないよう、ペットの種類や年齢を考えて正確に計算することが大切です。
適切な受託者や受益者、専門業者を見つけにくい
ペット信託を利用する際には、専門的に取り扱う業者が少ないことが課題の一つです。ペット信託は比較的新しい仕組みのため、業者同士の比較が難しく、それぞれの特徴やサービス内容を慎重に見極める必要があります。無料相談を活用し、複数の業者を検討することで、自分のニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。
また、信託財産を管理する受託者を見つけるのも簡単ではありません。受託者は帳簿作成や財産管理など多くの責任を負うため、引き受け手が少ないのが現状です。この問題を解消するには、信託財産を金銭のみに限定したり、負担に見合った報酬を設定したり、弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼するといった方法が考えられます。
遺留分の配慮が必要
信託財産は相続財産と分けて管理されますが、遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている財産の割合のことです。遺留分を侵害しないよう、信託財産の金額を慎重に設定する必要があります。適切に設定しないと、相続トラブルを招く恐れがあります。
ペット信託以外の法的な方法
ペットの世話を託す方法として、ペット信託以外にもいくつかの選択肢があります。
負担付遺贈
「負担付遺贈」とは、遺言書で「財産を渡す代わりにペットの世話をお願いする」と指定する方法です。たとえば、信頼できる家族や第三者にペットの飼育を頼み、その代わりに遺産の一部を渡す内容を遺言に記載します。
ただし、この方法には注意が必要です。負担付遺贈は、遺言で一方的に条件をつけるため、受け取る側がその条件を拒否する可能性があります。つまり、遺産もペットの世話も断られてしまうリスクがあるのです。
負担付死因贈与
「負担付死因贈与」は、負担付遺贈よりも確実にペットの世話をお願いできる方法です。この方法では、飼い主(贈与者)と世話を引き受ける人(受贈者)が事前に合意して契約を結びます。飼い主が亡くなった際に、財産の引き渡しとペットの世話が同時に発生します。
負担付死因贈与は、贈与者と受贈者が互いに納得して契約を結ぶため、死後に世話を断られる心配がありません。
ただし、適切にペットの世話が行われているかを監視する仕組みはないため、信頼できる相手を選ぶことが重要です。不安が残る場合には、ペット信託のように第三者の監督がある方法を検討したほうがよいでしょう。
元気なうちに専門家に相談
ペットは大切な家族の一員ですが、法律上は人と同じように財産を相続することはできません。そのため、飼い主にもしものことがあったときにペットの生活をどう守るか、事前に考えておくことが重要です。
ペット信託は、飼い主が病気やケガで世話ができなくなった場合や、亡くなった場合でも、ペットを安心して託すための有効な仕組みです。この仕組みを利用すれば、ペットの世話を引き継いでくれる人や必要な費用をあらかじめ準備し、安心できる環境を整えることができます。
ペットの未来を守るためには、元気なうちに専門家に相談することが肝心です。まずは、弁護士や司法書士などにペット信託について相談してみましょう。専門家に話を聞くことで、信託だけでなく、自分やペットに合ったさまざまな選択肢を提案してもらえます。
事前に計画を立てておけば、不測の事態が起きてもペットが安心して暮らせる環境を整えることができます。まずは専門家に相談し、大切な家族であるペットのための準備を始めましょう。
【関連記事】こちらもお読みください
- 死後事務委任契約とはどのような契約なのか?遺言書との違い等弁護士が解説
- 【おひとりさま遺産は国庫へ】倍増する国庫納付や遺贈について解説
- 【遺贈寄付とは】おひとりさま相続の選択肢|寄付との違いとは
- 【おひとりさま相続が増加中】生前対策を専門家に相談すべき理由