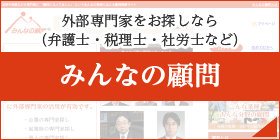【今から考えておきたい相続と山林】山林相続と管理を放置した時のリスク・デメリットなどを弁護士が解説

相続の話題で「空き家問題」はよく耳にするようになりましたが、実は同じくらい見過ごせないのが「山林」の相続です。
「山奥にある古い山林を相続したけど、使い道もないし、放っておいても問題ないだろう」そんなふうに思っていませんか?
しかし、山林を相続して登記や届出をせず、管理もしないままでいると、思わぬ損害や法的トラブル、行政からの指導を受ける可能性があります。さらに、2024年には相続登記の義務化がスタートし、「何もしない」ことがリスクとなる時代になりました。
本記事では、弁護士の視点から、山林を相続した際に注意すべきリスクやデメリット、そして具体的な対処法について解説します。相続を「受けるか迷っている方」「すでに相続してどうすべきか困っている方」どちらにも役立つ内容です。
1. 相続した山林を登記も届出もしない、管理も放置してしまうとどうなる
山林は一般の住宅地や宅地とは異なり、「使っていないから」と長年放置されやすい不動産です。しかし、相続後に登記や届出を怠ったり、管理を放棄してしまうと、法的・経済的に重大なトラブルが生じる可能性があります。以下では、放置によって生じうる3つのリスクを解説します。
登記しないリスク・デメリット(相続登記義務化への対応)
相続によって山林の所有権を取得した場合、2024年4月からは「相続登記」が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
山林は他人に貸す・売る・担保に入れるといった利用が難しいため、「名義を変えなくても困らない」と考える方が多いのですが、実はそれが大きなリスクです。たとえば将来山林を処分したくなったとき、被相続人名義のままでは売却も寄付もできません。また、子世代・孫世代へと時間が経過するうちに相続関係者が増え、「相続人不明・所有者不明の土地」となってしまうリスクもあります。
森林法の届出義務を怠ったリスク(市町村長への届出が必要)
平成24年(2012年)4月の森林法改正により、山林を相続・売買などで取得した者は、取得後90日以内に市町村長へ「所有者届出書」を提出する義務があります。
この届出を怠ると、20万円以下の過料が科される可能性があるうえ、自治体の森林施策(例:間伐補助、災害対策等)の対象から外されることもあります。また、近年は林地の適正管理が災害予防にも関係するため、「誰が管理しているのかわからない」森林は行政上の問題地として扱われかねません。
山林を管理しないことによるリスク・デメリット
さらに、山林そのものを放置しておくと、次のようなリスクが現実のものとなります。
- 不法投棄や不法伐採の温床となる
- 山火事・土砂崩れ等の災害時に損害賠償責任を問われる可能性
- 境界が不明確になり、隣接地所有者とのトラブル(越境、樹木の侵入など)
- 放置状態が長期化することで、土地としての評価額が著しく低下(またはゼロ)する
また、最近ではドローンや航空写真などで放置林の実態調査が進められており、従来のように「見つからなければ大丈夫」という考えは通用しなくなりつつあります。
2. 山林の相続時に取り得る対処
山林を相続することになった場合、放置することなく適切な対処を取ることで、将来のトラブルや不利益を防ぐことができます。ここでは、相続時に検討すべき主な対応策を紹介します。
① 相続するか放棄するかの判断を早めに下す
山林を相続する際は、「相続する」「相続放棄する」「管理や処分方法を決めたうえで相続する」など、最初の意思決定が極めて重要です。
使い道がなく、管理も難しいと判断した場合には、相続放棄を検討することが一つの手段です。
ただし、相続放棄は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、放置していると選択肢そのものが失われてしまいます。
なお、相続放棄をしても他の相続人が引き受けず、全員が放棄するケースでは、最終的に国庫帰属になるまでの間、管理義務が残る可能性がある点にも注意が必要です。
② 相続登記と森林法の届出を忘れずに行う
相続する意思がある場合は、相続登記(法務局への所有権移転登記)と、森林法に基づく市町村への届出の2つの手続きを速やかに行うことが重要です。
- 相続登記義務:2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内
- 森林法の届出義務:相続や売買などにより所有者が変わった場合、90日以内に届出(森林法第10条の7)
これらの手続きを怠ると、それぞれ10万円・20万円以下の過料の対象となり得ます。特に2024年以降は、法令違反のリスクが現実的なものとなっている点に注意が必要です。
③ 山林の活用・処分・管理方法を検討する
山林は、活用できる見込みがあるかどうかによって、対応方針が異なります。以下のような選択肢があります。
【a】自ら管理する
ご自身や家族が管理可能な場合は、林業の知識や外部委託も活用しながら維持していく方法が考えられます。
- 林業の知識や人脈がある方であれば、自営・委託による森林管理が可能
- 補助金を活用した間伐や整備も視野に(森林経営計画の作成が必要)
【b】他者に売却・寄付する
管理が難しい、もしくは必要性がない場合は、第三者への売却や寄付といった形で手放す方法も選択肢となります。
- 民間の山林バンクや林業会社、不動産業者を通じて売却可能な場合もある
- 市民団体や環境保全団体への寄付が認められるケースもある
【c】相続人の間で話し合いをして処分方針を決める
相続人が複数いる場合には、あらかじめ話し合いを行い、所有や管理の分担方法を明確にしておくことが重要です。
- 相続人が複数いる場合、共有状態を避けることがトラブル回避に有効
- 代表者一名に相続させて管理・処分を任せるなどの方法も検討
このように、山林の特性や地域性、管理可能性を踏まえて、現実的な選択を行うことが不可欠です。
3. 早めに専門家に相談
山林の相続には、相続登記や森林法の届出、管理方針の決定など、さまざまな対応が求められます。しかもこれらは、法律・行政手続・土地管理といった異なる分野にまたがるため、個人で処理しようとすると大きな負担になります。
見落としがあれば、後々深刻なトラブルや損失につながるおそれもあるため、できるだけ早い段階で専門家の力を借りることが大切です。
ここでは、山林相続において頼りになる主要な専門家をご紹介します。
① 弁護士:相続放棄・共有トラブル・損害賠償リスクに対応
山林相続に伴う法的なリスクを未然に防ぎたい場合、またはすでに問題が生じている場合には、弁護士への相談が有効です。
たとえば「相続を放棄したいが他に相続人がいない」「名義変更せずにいたら第三者とトラブルになった」といったケースでは、法的観点からの整理と適切な対処が必要になります。
弁護士に相談することで、以下のような対応が可能です。
- 相続放棄に関するアドバイスと家庭裁判所への手続き支援
- 相続人間の共有名義トラブルや意見の不一致に関する調整
- 不法投棄・山火事などによって発生する損害賠償リスクの有無と範囲の検討
- 相続放棄後の管理義務や、所有者不明土地に関する問題の法的整理
弁護士は、紛争の予防から、万が一の法的対応までトータルで支援できる専門家です。放置によるリスクを見極め、冷静かつ実務的なアドバイスを提供してくれます。
② 司法書士:登記義務に関する実務の専門家
相続登記は、法的に義務化された重要な手続きであり、専門的な書類作成と確実な申請が求められます。
申請ミスや不備による手戻りを避け、スムーズに名義を移転するためには、司法書士のサポートが非常に有効です。
具体的には、以下のような支援を受けることができます。
- 相続登記に必要な戸籍謄本や遺産分割協議書の収集・作成
- 登記申請手続きの代理とスケジュール管理
- 法務局とのやりとりや、土地の現況に応じた実務対応の選別
特に2024年4月から相続登記が義務化されたことで、期限内に適切な登記を行うことが「責任」として問われる時代になりました。
司法書士に依頼することで、法的リスクを回避しつつ、安心して相続手続きを完了させることができます。
③ 林業・不動産の専門家:管理・活用・処分を支援
山林の利活用や処分を検討する際には、現地に詳しい林業関係者や不動産の専門家のアドバイスが不可欠です。
山林の資産価値や管理の可否は、地域の状況や土地条件によって大きく左右されるため、専門的な見立てが必要になります。
たとえば、次のような支援が受けられます。
- 山林の資産価値や管理可能性の診断
- 森林組合や林業会社による間伐・保全・伐採計画の策定支援
- 山林専門の不動産業者による売却・寄付・山林バンク活用の提案
山林は宅地や建物と異なり、市場性が低く、放っておけば価値が下がるリスクもあります。価値ある森林として活用するか、不要な負担として手放すか――的確な判断には、現場の事情に通じたプロの知見が欠かせません。
④ ワンストップ対応の窓口も活用を
自治体や民間の「相続相談センター」では、司法書士・弁護士・不動産の専門家が連携して、相続に関するトータルな相談に応じています。これらの窓口は、相談料無料・初回相談可といった形で利用しやすく整備されている場合が多く、まずは気軽に情報収集をする場としてもおすすめです。
【まとめ】山林相続を「見て見ぬふり」しないことが将来の安心につながる
山林の相続は、「空き家」ほど目立たないものの、実は放置リスクの大きい相続財産です。
登記を怠れば過料の対象となり、森林法上の届出を忘れれば行政対応の外に置かれ、管理を放棄すれば思わぬ損害賠償責任が発生することもあります。
特に2024年以降は、相続登記が義務化され、「知らなかった」「使っていないから」は通用しない時代に突入しました。
とはいえ、すべてを一人で抱える必要はありません。弁護士や司法書士、不動産・林業の専門家といった信頼できるパートナーに相談すれば、リスクの把握から対応まで、着実に道筋を立てていくことができます。
大切なのは、「あとでいいか」と先送りせず、今のうちに自分の山林と向き合っておくことです。
将来、子や孫の世代に“負の遺産”を残さないためにも、早めの確認・行動をおすすめします。
【関連記事】こちらもお読みください
- 2025年問題により大相続時代突入【今から考えておきたい相続と空き家】
- 相続登記を義務化する改正法が成立、2024年4月までに施行されます!
- 実家の不動産(土地・建物)を相続する手続きと相続したくない場合の対処方法を解説