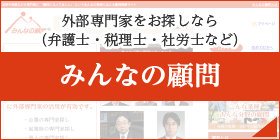【大家業・不動産賃貸業の相続】親がアパート・マンション経営をしていて相続になったら考えること
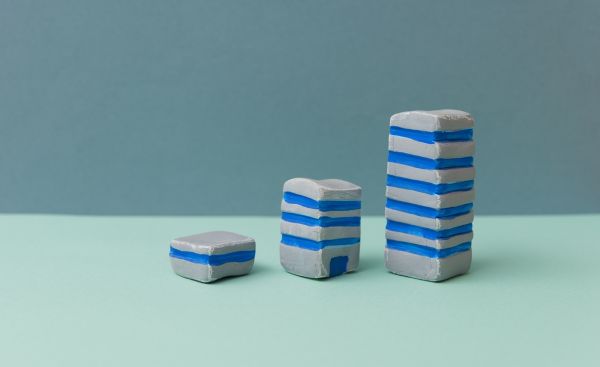
親がアパートやマンションを経営していた場合、その不動産は「収益物件」として相続財産のひとつになります。相続人にとっては「資産」とも言えますが、同時に「管理や手間、借金などのリスク」を引き継ぐことにもなります。
とくに大家業には、入居者対応や修繕、確定申告など、思っている以上に手間のかかる仕事も多く、経験や知識がないまま引き継ぐと、思わぬトラブルを招くこともあります。また、収益物件はお金の価値だけでは分けにくく、遺産分割でもめやすい財産の一つです。
この記事では、親のアパート・マンション経営を相続することになったときに、まず何を考えるべきか、引き継ぎの判断ポイント、遺産分割の注意点、相続後の対応まで、専門家に相談するタイミングも含めてわかりやすく解説します。
目次
親がアパート・マンション経営をしていて相続になったら、最初に考えること
親が亡くなったあとに、アパートやマンションなどの「収益物件」を相続することになったとき、まず考えるべきことは、「この不動産を相続するべきかどうか」です。なぜなら、収益物件にはお金を生み出すメリットがある一方で、管理や修繕、税金、借入金などの負担もあるからです。
相続した不動産に「どれくらいの価値があるのか」「借金は残っていないか」「賃貸経営はうまくいっているか」などを冷静に調べる必要があります。特に、次のようなポイントをチェックしましょう。
- 建物の築年数や劣化状況
- 空室の数や入居者の家賃滞納
- 家賃収入と支出(ローン返済、固定資産税、修繕費など)のバランス
- 不動産の名義(親の単独か共有か)
- ローンの連帯保証人になっていないかどうか
こうした情報を整理することで、「この物件を引き継いでも問題ないか」を判断しやすくなります。
まずは慌てず、専門家と一緒に相続財産の全体像を確認することが重要です。
アパート・マンション経営を引き継ぐのか?リスクはないのか?
アパートやマンションを相続したあと、そのまま「大家さん」として賃貸経営を続けるか、それとも売却するかを選ぶ必要があります。ここでの判断は、将来の生活や資産運用に大きな影響を与えるため、慎重に考えましょう。
賃貸経営を引き継ぐ場合に考えるべきこと
アパートやマンションの経営を引き継ぐかどうかを判断するには、「自分が本当に大家としてやっていけるのか?」を冷静に見極めることが大切です。
次のポイントを確認してみましょう。
① 物件の収支は黒字か?
家賃収入があっても、ローンの返済、固定資産税、修繕費、管理費などの支出が多ければ、実際には赤字になることもあります。帳簿や通帳を見て、どれくらいお金が残っているかを正しく把握する必要があります。
② 建物の状態はどうか?
築年数が古い物件は、入居者が集まりにくかったり、大規模な修繕が必要になることもあります。建物の状態や入居状況をチェックし、今後の維持コストを想定しておきましょう。
③ 誰が経営を担うのか?
相続人が複数いる場合、「誰が日々の管理や修繕の判断をするのか」「収益をどう分けるのか」など、役割分担を明確にしておかないと、後でトラブルになる可能性があります。
④ 本業や家庭との両立はできるか?
大家業は手間がかからないと思われがちですが、実際は入居者対応や契約更新、設備トラブルなど、対応すべきことが多くあります。本業や育児などと両立できるかを事前に考えておきましょう。
⑤ 専門知識や経験はあるか?
不動産経営には、税金や契約、建物管理の知識が必要です。経験や知識がないまま始めてしまうと、思わぬ損失を出してしまうこともあります。不安がある場合は、不動産管理会社や税理士などの専門家の力を借りるのが安全です。
アパート・マンションなど収益物件の遺産分割のポイント
アパートやマンションのような収益物件は、「お金を生み出す資産」である一方で、「簡単には分けられない財産」でもあります。現金や預金と違い、物理的に分けることができないため、相続人の間でトラブルになりやすいのが特徴です。
収益物件を含む遺産をどう分けるかを決めるには、まず「どれだけの価値があるか」「今後も利益を生み出すか」「管理できる人がいるか」といった点を整理することが大切です。
そのうえで、以下のような選択肢を検討するのが一般的です。
① 誰か一人が相続し、他の人に代償金を支払う
収益物件は、建物そのものを分けることができないため、相続人のうち誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には「代償金(だいしょうきん)」というお金を支払ってバランスを取る方法があります。
代償金とは、特定の相続人が遺産の一部(たとえばアパートやマンションなどの不動産)を単独で取得したときに、他の相続人の相続分を補うために支払うお金のことです。
たとえば、長男がアパートをすべて相続し、弟や妹にはその相応額の現金を支払うといった形です。これは実務でもよく行われている方法で、不動産の管理責任や収益を一人に集中させることで、後々のトラブルを防ぐ効果もあります。
ただし、注意点として、代償金を支払う側にはそれだけの資金力が必要です。手元に十分な現金がない場合は、金融機関からの借り入れや不動産の一部売却が必要になることもあり、負担が大きくなる可能性もあります。
② 売却して、得たお金を分ける
収益物件を誰も引き継がずに売却し、得たお金を相続人で分け合うという方法もあります。この方法のメリットは、「現金というかたちで平等に分けやすい」という点にあります。物件を相続した人が他の相続人に代償金を支払う必要もなく、公平感が得やすいのが特徴です。
たとえば、3,000万円で売却できた場合、3人の相続人がいれば、1,000万円ずつ分けるといったシンプルな手続きが可能です。相続人同士で利害が対立しにくいため、早期に合意を得やすいのも利点です。
一方で、注意点もあります。不動産は、希望する金額ですぐに売れるとは限りません。特に地方物件や築年数が古いものは、買い手が見つかるまでに時間がかかることもあります。また、売却したときの利益に対しては譲渡所得税がかかる可能性があるため、税金の計算にも注意が必要です。
売却を検討する場合は、事前に不動産会社などに査定を依頼し、市場価格を把握してから相続人全員で話し合うのが現実的です。
③ 共有名義で相続する
不動産を相続人全員で「共有名義」にして相続する方法もあります。この方法は、「誰が取得するか決めきれない」「売却もすぐにはできない」という場合に、一時的な対応として選ばれることがあります。
共有名義とは、ひとつの不動産を複数人で持ち合う状態のことです。たとえば、3人で相続すれば、それぞれ3分の1ずつの持ち分を持つことになります。
一見すると平等で便利に見えますが、実際にはトラブルが起きやすい方法でもあります。たとえば、建物の修繕や入居者との契約、将来の売却など、何をするにも共有者全員の合意が必要になります。一人でも反対すれば話が進まなくなることも珍しくありません。
また、将来的に相続人の誰かが亡くなり、その持ち分をさらに次の世代が相続すると、所有者が増えて権利関係が複雑になっていきます。こうした状態になると、「誰も動かせない不動産」になってしまうリスクもあります。
そのため、共有名義は「一時的な措置」として検討するにとどめ、できるだけ早めに名義を整理することが望ましいです。どうしても共有せざるを得ない場合は、相続後の管理方法やルールをあらかじめ話し合い、書面で残しておくことが重要です。
アパート・マンションを相続した後の流れ
アパートやマンションの相続は、「もらったら終わり」ではありません。正式に自分のものとして扱うためには、いくつかの手続きをきちんと行う必要があります。また、経営を続ける場合には、管理体制や税務の対応もすぐに始めなければなりません。
ここでは、不動産の相続が決まった後にやるべき基本的な流れをわかりやすくご紹介します。
① 不動産の名義変更(相続登記)
まずは、親名義になっている不動産の所有権を、自分(または相続人全員)の名義に変更する「相続登記」を行います。これは法務局で行う手続きで、放っておくと、将来の売却や融資などがスムーズに進まなくなってしまいます。
2024年4月からは、相続登記が義務化されており、正当な理由がないまま3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあるため、早めの対応が必要です。
② 管理会社との契約見直し・引き継ぎ
すでに管理会社に委託していた場合、相続によってオーナーが変わったことを管理会社に伝え、契約内容を見直します。契約の名義変更や連絡先の更新などを行い、入居者対応や家賃の入金先も新しい体制に切り替えます。
自主管理をしていた場合は、今後も自分で管理するか、外部に委託するかの判断が必要です。
③ 入居者への通知と対応
入居者に対しては、「大家が変更になったこと」を文書などで丁寧に通知します。家賃の振込先を変更する場合や、連絡窓口が新しくなる場合には、トラブル防止のためにも早めの案内が大切です。
あわせて、各部屋の賃貸借契約書を確認し、更新期限や家賃滞納の有無、設備の不具合などがないかもチェックしましょう。
④ 税務申告と相続税の手続き
不動産を相続した場合、相続税の申告が必要になることがあります。相続税には申告期限(原則として死亡から10か月以内)があるため、早めに税理士などに相談して、必要書類の準備や財産評価を進めておきましょう。
また、相続後の賃貸経営から得られる家賃収入は、「不動産所得」として確定申告が必要です。親が申告していた帳簿や収支記録が残っていれば、それを引き継いで整理しておくとスムーズです。
⑤ 長期的な経営方針を立てる
最後に、「この不動産をどう活用していくのか」を中長期的に考えておくことが重要です。
今後も安定して収益を上げられるのか、リフォームや建て替えが必要になるのか、将来的に売却すべきかなど、将来の見通しを立てることで、無理のない経営が可能になります。
不安や迷いがある場合は、不動産会社、税理士、司法書士などの専門家とチームを組んで対応することをおすすめします。
早めに専門家に相談
アパートやマンションなどの収益物件を相続するときは、早い段階で専門家に相談することがとても重要です。不動産の相続には、税金、登記、管理、遺産分割など、複数の専門知識が必要となるため、自分ひとりで判断するのは危険です。
たとえば、収益物件の評価額によっては相続税がかかる場合があり、申告が遅れると追徴課税や延滞税などの負担が発生するおそれがあります。財産の評価方法や、相続税の特例が使えるかどうかは、税理士などの専門家に確認してもらうことで、適切に対処できます。
また、兄弟姉妹など他の相続人と「誰が相続するのか」「どう分けるのか」で意見が対立することもあります。こうした場合には、第三者である弁護士に相談し、冷静に話し合いを進めてもらうことで、トラブルを避けやすくなります。
さらに、物件を引き継いだあとに賃貸経営を続ける場合は、不動産の管理体制や経営方針を見直す必要があります。家賃の入金先や入居者対応、修繕計画など、現実的にこなせるかどうかも重要な判断材料です。不安がある場合は、不動産会社や管理会社と連携して、安心して経営できる体制を整えるとよいでしょう。
収益物件の相続は、金額も大きく、関係する法律や手続きも複雑です。感情だけで判断したり、その場の話し合いだけで決めてしまったりすると、後から後悔する結果になることもあります。だからこそ、専門家のサポートを受けながら、事実に基づいた判断を積み重ねていくことが大切です。
相続が発生してから慌てるのではなく、少しでも不安や疑問を感じたら、早めに信頼できる専門家に相談しておくことをおすすめします。
【関連記事】こちらもお読みください
- 2025年問題により大相続時代突入【今から考えておきたい相続と空き家】
- 相続財産に【非上場企業の少数株式】が含まれていた場合の対処
- 事業承継を相談できる専門家、機関をパターン別に解説
- 不動産登記手続きをスムーズに行う方法